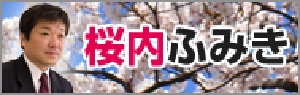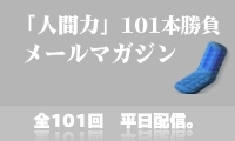「究極のゲームの理論活用法」は、このレベル
手塚 「組織というものを、いかにも人格のある合理的なプレイヤーとしてゲームをプレイする存在であると考えるべきかどうか」ということです。
一般的にはそのような企業観があって、「アサヒビールとキリンビールがどうやって戦っているのか」としか見られていませんが、それぞれの組織には独特の内部のルールとか掟があるんです。ある組織にとって合理的なことが、必ずしも他の組織には当てはまらない。合理性の基準が違うかもしれないわけですね。それぞれの組織が元々どういう歴史で発展してきて、どういう仕事のやり方をしているか、物事を判断するパターンを持っているかを考えなければならない。
例えば「より新しいものを好む」考え方をするか、「伝統的なものを好むか」ということで、まったく違う行動パターンが出てくるでしょう。
運営者 ほうほう、面白そうな話じゃないですか。
手塚 さらに実際の意思決定はどのようにして行われるかというと、組織の中にいる何百人もの人が、意思決定がある方向に傾いていく空気を作っているはずなんです。
ここのところはものすごく分析が難しい。例えばクリントン政権の経済政策はどうやって作られているかという問題を、クリントン個人の性格に還元して話すのはものすごく簡単な話です。しかし実際のところはそこに何千人という人々が関わっていて、あらゆるプロセスを経て最終的な組織のアウトプットという形で政策が形作られている。その中にいる人々がどのような政治的なポジションも取っているかというところまで分析しなければ、意思決定の構造が説明できないわけです。
運営者 もしそこが把握できていれば、相手が交渉の時に何かを提案をしてきたり、あるいは新しい競争を仕掛けてきたりしたときに、どういう条件を出せば相手が折れるか、どこを攻撃すれば相手が崩れるかがわかるわけですよね。
手塚 というところまで掘り下げて、ゲームをやるというのが、究極のゲームの理論活用法なんです。
運営者 でも実際のビジネスの世界では、そのレベルに近いところでの競争が行われているわけだから、その方法を知らなければ勝つことはできない。そこから先のことは、「ゲーム理論活用術,-儲けるための経済学を学ぶ」を読んでね、ということなわけですね。
手塚 答えが書いてるかどうかということは別にしてね。
運営者 それじゃ売り文句にならないじゃないですか。